���ʼn�O�l�W
���ʼn�O�l�W���L���ɗ��Ă���Ƃ����̂ł����́h�W����ӏO�l�g�h�ŏo�������B
���ۓI���x���̎d�����Ȃ��A�Ǝ��̐��E��z�����O�l�̊e�l�e�l�̌��I�Ȑ��E���P�Q�V�_�̍�i��ʂ��Ċ����邱�Ƃ��ł����B���ʼn���n�߂�����ł����ڂ����͒m��Ȃ��Ƃ͂����A�Z�@�ȂǑ����͐������ł��A�����[���ӏ܂����B
���J�쌉�i1891�`1980�j�̓��]�`���g�i�}�j�G�[���@�m���[���j������ɕ����������ʼn�ƂƂ��Ēm���Ă��邪�A�\��L���ȃ��m�N���[���̐��E�������ɂ������B�Õ�����̂Ƃ�����i�̉��[���ƁA�Â����A�������͂ǂ����炭��̂��낤�B�ڂɌ�������̂̉��ɔ������̍�����T�����Ă��̂��낤���Ǝv�����i���������������B������܂��ł͂���̂������ׂĂ��u�S�����߂āv�̈�ۂ������V�N�������B���]�`���g�̍�i�ɂ��Ă͖��邢�u��q�K���X�ɑ}�����A�l���l�Ƒ��ԁv���Y����Ȃ��B
�l���z�O�i1909�`2000�j�̓J���[���]�`���g���n�߂����Ƃł����Ă���B������Ƃ��Ȃ�����A�ԁA�A�����d�˂ē�����ʼn�Ɠ��̓������̂���F�ʂ���i�ɕ\��������炵�Ă���B��A�ʕ��A�L�k�A���Ƃ������悤�Ȑg�߂ɂ��郂�`�[�t���L����Ԃɕ����яオ�点�A�������ꂵ���ґz�I���E�����o���Ă���B�ʎ��I�ɕ\�����ꂽ����I�f�ނ͍�i�̒��œ��퐫�����I�u�W�F�ƂȂ��Ă���B
���N�Y�i1920�`1976�j�͐��U�ɂ킽��G�b�`���O����������Ȃ����B
�O�l�̒��ł͗B��A���ۓI�ɁA���邢�͌��z�I�Ɏ��Ȃ̓��ʂ�\�����Ă���B�ꌩ�q���̊G���Ǝv����悤�Ȃ��̂�����A���Ă��Ă����ȑz�����L����Ƃ����_�Ŋy������i�����������B�p�E���E�N���[�̉e�����Z���Ƃ���Ă���B
���̈���A�@�ׂŎʎ��I�ȃ^�b�`�ŕ`�������╗�i�Ƃ����̂��������B
�Z�@�����낢�뎎���Ă݂��Ƃ����Ղ���݂Ƃꂽ�B
|
|
�A���N�T���_�[�E�J���_�\
�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@���쌠�̂��߉摜�͓\��܂���B
���������L���܂ŗ����̂����炱�̓W��������Ă������Ƃ������ƂɂȂ���p�ق��͂��������B�����Ɏ��ʂ������̂�����ƈ�e���̗Ⴆ�ʂ�ɍ������Ă��܂��č�������̂����A�S���W���������Ⴄ��ɑz���ȏ�̂����W����Ŗ����������b�オ�������B
���w�̔��p�̎��ƂŃv���X�e�B�b�N�̃J���[�V�[�g���g���ă��r�[�������y�����𖡂�������Ƃ�����B�V�䂩��݂邷���r�[�����D���ɂȂ����̂͂����Ƃ��̑̌��Ɩ����ł͂Ȃ��Ƃ�������̂����A������n�߂��l�����̐l���������Ƃ����̓W����ł͂��߂Ēm�����B
�W����Ԃ��L���̂ŁA���Ȃ蒷���Ԓ��J�Ɍ����̂������������Ȃ������B�����Ɋւ���m���͂قƂ�ǂȂ��ɓ������������A�W����̋L������A���邢�͐}�^���Q�l�ɂ��Ď��ȗ��ɂ܂Ƃ߂Ă݂�͎̂��́m�m�肽���~�v�ɂƂ��Ă��Ȃ�y������Ƃ��B
�`�����������������@�b�����������@�i1898�`1976�j�@�A�����J
�u���r�[���v�Ɍ�����悤�ɒ����ɂ�������������A�\���̉\����傫���L���邱�Ƃɂ��ߌ�����p�ɑ傫�ȉe����^�����A�A�����J�̒����ƃA���N�T���_�[�E�J���_�\�̓W�����
�����ǂ��Ȃ���S��SECTION�ɕ����Ĕz�u����A�͂��߂Ă��̌|�p�Ƃ̑S�e��m�肽���҂ɂƂ��Ĕ��ɕ�����₷����悾�����B
SECTION�T�@�@�@�P�X�Q�O�N��`�P�X�R�O�N
�����A�G���W�j�A���u���@�B�H�w�̊w�ʂ��擾�A�w�⓮�͊w���K���������Ƃ��Ȍ�̒����ƂƂ��Ă̑f�{����ނ��ƂƂȂ�̂����A�G���W�j�A�����A�Ƒn�����\���ɐ������镪������߂Č|�p���u���A�Q�T�ɂ��Ĕ��p�w�Z�ɓ���B���̂���̖��G��A�����̂��铮���̑f�`���W������Ă���B
�����̑f�`�̍˔\�������A�j���[���[�N�́u�i�V���i���E�|���X�E�K�[�b�g�v���ő}�G�̎d�����J���_�\�͂��̎�ނŒʂ����T�[�J�X�Ƃ̉^���I�o����A�I���J��Ԃ��㉉����邱�ƂƂȂ����A�u�J���_�\�̃T�[�J�X�v�̖��J���ł������B
�P�X�Q�U�N�͂��߂ăp���ɑ؍݂��A�܂��Ȃ��A�A�g���G�ɐ���������Łu�J���_�\�̃T�[�J�X�v�����������B�j���Ƀu���L��R���N��ؕЂȂǂ������F���č�����A�ۂ�A���C�I���A�����A�y�Ǝt�A�j�n��Ȃǂ���Ȃ�u�T�[�J�X����v�B�A�����łȂ����������͓��L�̓������\�ŁA����̎�ő������̂����A����̂ɍ��킹�ă��[�����X�ȓ�����������T�[�J�X����͂����܂��A�p���̌|�p�Ƃ�Ⴂ�A�����J�l�̊Ԃŕ]���邱�ƂƂȂ�B
���ɐݒu���ꂽ�X�N���[���ŃJ���_�\��������u�T�[�J�X����v�̃r�f�I�����邱�Ƃ��ł������A�j���l�`�̓����ɐl���ɂ����邨���������������B�����đ̊i�̂��������炭�ӔN�̃J���_�\���܂�ŏ��N�̂悤�Ɋy�������ɉ����Ă����̂��Y����Ȃ��B
�T�[�J�X�ɗp�����j���̎��R�ȋȐ�����͐j����������ɐG�����ꂽ�f�`�����܂�邱�ƂƂȂ����B�W�����ꂽ�����̐j�������̂����A������ԋC�ɓ������̂͂P�X�Q�W�N��́f�d���������������f�Ō�ɉ�W���݂Ȃ��瑢�����̂������B�u���̓��ӂƂ�����M�����v�ƃJ���_�\���M�������Ă���悤�ɁA���̏ۂ͂܂�������M�����łP�{�̐j���ŗ��̓I�ɍ���Ă����̂��B
SECTION�U�@�P�X�R�O�N��`�S�O�N�㏉
�P�X�R�O�N�A�����h���A���̃A�g���G�������˂��J���_�\�͂����Ŗڂɂ����w�I���ۊG��ɋ��������Ƃ���B�����āA���̉�ʂ������o������ǂ�Ȃɑf���炵�����낤�Ɛ[�X�Ɗ����������������B
���ۂɖڊo�߂��J���_�\�͎���u�������āA�j���A�S�A�ؕЂȂǂ�p���Ē��ے����Ɏ��g�ށB
�}���Z���E�f���V�����ɂ�������r�[���Ɩ��Â���ꂽ���������̐���Ɏ��g�ޏo�����̂͂P�X�R�P�N�̂��ƁB��W�ɃJ���_�\�̌��t�Ƃ��Ă���ȋL�q���������B�u��i�̂���{�Ƃ��ĉF���̑̌n�ɏ�ɐS��D���Ă����B�E�E�E�E���ɕ����ԓV�̂ɖ�������Ď��͍ŏ��̃��r�[���𐧍삵���v
�肪�������r�[���́A�蓮���r�[���A���[�^�[�ŋK���I�ɓ������[�^�[���r�[���A���u������X�^���f�B���O���r�[���A��C�̗���ɂ���ĕs�K���ɐ���n���M���O���r�[���ȂǁB
���r�[���ɐ�삯�āA���삪�n�܂����̂́A�����Ȃ������X�^�r���ƌĂ����̂�
�Ȍ�C���r�[���ƃX�^�r���̓J���_�\�̐l�C�V���[�Y�ƂȂ肻�̖��������߂��B
���̂r�d�b�s�h�n�m�ŐS�Ɏc�����̂͐^���ԂɃy�C���g���ꂽ�X�^�r���h�s�����@�s�@�s�������h�ƃn���M���O���r�[���́h�a�������������������h
SECTION�V�@�P�X�S�O�N��
�P�X�S�O�N��ɂ̓A�����J���\����A�[�e�B�X�g�Ƃ��Ă̖����͊m������̂ƂȂ��Ă����B
�펞���ɂ����Ă��n��ӗ~�͐����邱�Ƃ�m�炸�A���荢��ȋ����̑���ɖ��g���Đ��삵���B���̂���̍�i�ɂ̓~����C���E�^���M�[�Ƃ������V���[�����A���X�g�̉e��������Ƃ����B
���́A�Ăы�����p���A���r�[����X�^�r������邪�����ɂ͂��������z�C����������A���R�ȑ��`���W�J����Ɠ����ɂ��傫�ȋ�ԂƂ̂����������悤�ɂȂ�B���z��ԂƂ̈�̉��Ƃ����X�P�[���ւƔ��W����B
��������A�W���G���[�ɂ����g�ށB����͂������ċM���g���������ȑf�ނł͂Ȃ��j���A���A�K���X�Ƃ���������e����ł����f�ނő����A�����ď��i�����邽�߂̂��̂ł͂Ȃ������悤���B
���̂r�d�b�s�h�n�m�ŋC�ɓ������̂́h�r���������@�o���������h�@�h�q�����C�v���������Cand Blue on Black"
���̑薼����������ł��邪�A���̌��t�����p����Ɓu�����Ƃ��d�v�Ō������Ȃ��F�͔��ƍ��̂Q�F�ł���B����ɐԂ�u���A���̔��Α��ɐ�u���B�̋߂��ɂ͉��F�ƃI�����W�F�����������B��������ł͂Ȃ��B���̐F�ɂ͋������Ȃ��v�ƁB������i�̒��F���A���̌�ɑ������ɃO�A�b�V���ŕ`����钊�ۉ�ɂ��g��ꂽ�F�͂��̌��t�ʂ�B�������Ȃ��̂��B
SECTION�@�W�@�@�P�X�T�O�N��~�V�O�N���@
�������^�������X�^�r���͂₪�ăA�g���G�ł͐���s�\�ȃ{�����[���ƂȂ�A�H��ɂ����ďn�������Z�p�H���w�����Ă̐���ƂȂ�B�Ⴂ���ɐg�ɕt�����H�w�̒m�������Ĉړ��̂��߂ɕ�������H�v���Â炳�ꂽ�B���̈�A�~�V�K���B�̃O�����h���s�b�Y�Ƃ������ɂ���k���@�f�����������@�u�������������Ƃ�����i�͂P�R�P�O�D�U�~�X�P�S�D�S�~�P�U�S�T�D�X�p�Ƃ�������Ȃ��̂ŁA�Ԃ��h��ꂽ���̒����̓r���̑O�̋�Ԃɓ��X�Ɨ����A���ꎩ�͓̂������Ƃ͂Ȃ������̎����l�X����������ʂ蔲������ł���Ƃ����̂��J���_�\�̈Ӑ}����Ƃ���̂悤���B����̓J���_�\����ɂ�邻�̒��ԃ}�P�b�g���W������Ă����B��^�̃X�^�r���̓��V���g���A�j���[���[�N�A�p���A�t�����N�t���g�Ȃǐ��E�e�n�ɂ���Ƃ������Ƃ��B
�����ȍD��S�̕����܂܂ɃJ���_�\�̕\���̈�͐l�X�̊��҂ɂ������邩�̂悤�ɍL�����Ă����B
�����O�̗z�C���ƂĂ炢�̂Ȃ���ʂ̑傫���������u�T���f�B�v�u�W���C�A���g�`���C���h�v�Ƃ��������̂ŒN��������ꂽ�l���ł������悤���B
���{�̔��p�ق�����o�i����Ă����B���ł��쑺�L�O���p�ق�K���@��͂���ΐ�ɂ������h�s�����@�s�@�s�������h��ŔӔN1976�N�́h�e�������@�v���������@�c�������h�ɉ��͂����B
|
|
�C�^���A�E���l�T���X�W
�P�T���I����P�U���I�ɂ����ăC�^���A�ŊJ�Ԃ������ʂȌ|�p�I�v�V�̓t�B�����c�B�G��M���Ƀ��F�l�c�B�A�A�~���m�œW�J���ꂽ�����ꂼ��̓s�s�ő�K�͌��z�������i�����߂����̌��͎҂ɗi�삳��n��ɘr���ӂ�����|�p�Ƃ�H�|�E�l���o�ꂵ���B���j���c���ɁA�s�s�������ɂ��ďЉ��u���l�T���X�����v�̓W����ŁA�S�y����W�߂�ꂽ�Ƃ����G��A�H�|�i�ȂǂU�V�_�̍�i�Q�͂S�̃e�[�}�ɕ�����ꃋ�l�T���X���킩��₷���Љ�Ă����B
���֓���ƂȂ�Ƃ����l�̑������낤�I
�܂��A�t���E�A���W�F���R�́u����̌����v�Ől�X�̓������~�܂��Ă����B����𗐂��Ȃ����x��
�h�E���ǂ݁h�������B�łȂ�����͂Ă����������B
�W���ɉ����Ă����܂��ɏ����o���Ă݂��E�E�E�E
�T
�P�T���I�O���̓`���Ɗv�V�����āA���̌�̌|�p�j�Ɍ���I�e����^���邱�ƂƂȂ����u���ߖ@�v�̓o�ꂪ�݂����i�Q�B�Ō�̋P����������Ƃ����ʐF�ʖ{���������B
�u���l�b���X�L�ɂ��T���^�}���A�f���t�H�I�[���吹���́u�N�[�|���̖͌^�v�A�������c�H�E�M�x���e�B�́@�u�V���̖�̕�������v�ȂǁB���ɂ��̔������F������ۂɎc��̂̓t���E�A���W�F���R�́u����̌����v�B
���ߖ@�����Ď���{�b�e�B�`�F�b���̃t���X�R��u��ٍ��m�v�B
�U
���ߖ@����b�Ƃ��ăC�^���A�S�y�ɍL�����Ă����e�n�ŋ}���ɕω����Ă����\�����@���Љ�B
�W����i��
�����C�^���A�̉�Ƃ́u���z�s�s�̕��i�v�A�A���h���A�E�}���e�\�j���́u���Ƒ��v�Ȃ�
�V
���z���`�������Č��ꂽ�Ƃ������鐷�����l�T���X�͂P�T�O�O�N����̂Q�O�N�ԁB���I�i���h�E�_�E���B���`�A�~�P�����W�F���A���t�@�G�b���̊��鎞��B
�����Ĕ������l������h�����鑽�l�ȗ���u�}�j�G���X���v�̋N���B
���̃R�[�i�[�̓W����i�Ŗڂ��Ђ����̂͂�͂�A��L�̎O�҂̍�i
���I�i���h�́u�l�̂̔��v�~�P�����W�F���̒����u�u���[�^�X�v�p���t���b�g�������Ă������t�@�G�b���́u���E���F���|�^�v
�W
�F�ʏd���������F�l�c�B�A�Ǝ��������i�ɕ\������Z�@���d�������t�B�����c�F�Ƃ����ΏƓI�ȓ�̗�������B�W���̂��߂�����͑S���[���b�p�Ƀt�B�����c�F����L�߂�������ʂ������������Ƃ̐��ʁA���H�A���U�C�N�A����A�^�y�X�g���[�Ȃǂ��Љ�Ă���B
�W���̓e�B�c�A�[�m�u�t���[���v�A�p�I���E���F���l�[�[�u���s�e���ɑ��q�A���e�\���X���Љ�郔�B�[�i�X�ƃ����N���E�X�v�����āA�V�j�����[�A�L��̃��U�C�N�A�t�H���e�k�I�[���@�̐���̊��A�ȂǁB
������͂��̐p�����f�b�T���Ȃǂɂ悭������u���[�^�X�Ƃ̏o��A�������ʖ{���������Ƃ����n�������B
|
|
��
| 2002�N |
�T���g���[�~���[�W�A���V�ێR |
�G�b�V���[�W

�U������q�������p�ɋ��������n�߂��̂ňꏏ�ɍs�������Ƃ����`���Ƃ͂��߂Ĉꏏ�Ɍ����W��������B���������T���g���[�~���[�W�A���V�ێR�͈������Y����v�̎a�V�ȃf�U�C���̔��p�فB�ߌ�����p�𒆐S�Ɉ����Ă���Ƃ����̂����̓����Ȃ̂������َ҂̏��Ȃ��łQ�O�P�O�N�ɂ͕قƕ������B���Ƃ����s����T���Ă��Ă���͂ǂ��������Ƃ��낤�B�����ł͂��肦�Ȃ��Ƃ��v���̂����l�X�̚n�D���ߌ���ɂ͂Ȃ��Ƃ������Ƃ��B�E�E�E�E��Ƃ͍̎Z������Ȃ����͐��Ă����Ƃ������Ƃ��낤���������C������B�n���e�n�ɂ��ꎞ�ɂ�������̔��p�ق��ł������L�Ӌ`�Ɋ��p����Ă���Ƃ���͏��Ȃ��̂ł͂Ȃ����B���X��������Ă݂͂邪�ՎU�Ƃ��Ă��邱�Ƃ������B
Maurits Cornelis Escher,�i1898�N - 1972�N�j�I�����_�̔ʼn��
�G�b�V���[�Ƃ̏o��͗F�l�������Ă�����W�������悤�ɋL�����Ă���B�Ռ��I�������͓̂�̎肪���݂��̎��`���Ă���u�`����v�������B
�ٓ��̓G�b�V���[�̕s�v�c�̐��E�ɖ����Ă����B�E�b�h�J�b�g�A���g�O���t�A���]�`���g�Ƃ������ʼn�Z�@�ŕ\�����ꂽ���ɗނ̂Ȃ��Ƒn�I��i������ł����B���z�s�\�ȍ\�����A�A������L���̂Ȃ��ɕ����߂����́A���ʂ��p�^�[���Ŗ��ߐs���������̂ȂǁB
�W�O�\�[�p�Y���̂悤�ɕ��ʂ����̃p�^�[���Ŗ��߂Ă������@�̓X�y�C���̗��łł������A���n���u���{�a�̃��[�A�l�̃��U�C�N�͗l����C���X�s���[�V�������Ƃ������Ƃ͂悭�m���Ă��邪�A�y�؋Z�p�҂ł��������A�����w�҂ł������Z�Ƃ����������܂��A�G�b�V���[�̐��w�I�\�}�ɏ��Ȃ��炸�e�����Ă���̂ł͂Ȃ����Ǝv�����B
��ȍ�i��
�g�����ʂ����ɋ��ƒ��̃p�^�[������������ �w��Ɛ��x�A�V�������ߖ@�̂�������������w�K�i�̉Ɓx�A���ۂɂ͍�邱�Ƃ��ł��Ȃ����[�v��K�i���̂ڂ葱����l�Ɖ��葱����l��`����
�w�㏸�Ɖ��~�x�Ȃ�
|
|
| 2002�N�@�@�@�@�@�@�@ |
�����s���p�� |
�}���N�E�V���K�[���W

�U���P�T���A�v���Ԃ�ɓ����s�����p�ق֓��ق����B��t���Ő��ʉ�O���[�v�ɓ����Ă����������ւ͂悭�����^�����ɉ��������B�ŏ��͊G�̐搶���o����鐅�ʘA���W�����邽�߁A�����Đ�t�𗣂�鏭���O�A�����܂����l�̒��ԂƂƂ��ɂ��̓W����ɓ��I�����̂ł������B���̂܂ܐ�t�ɂ��ꂽ�炻�̌�����x���K�ꂽ�ɈႢ�Ȃ��Ɖ߂��������v�����B
���傤�ǁA�V���K�[���̓W����������B�V���K�[���P�Ƃ̓W���������̂͂P�X�X�O�N�ȗ��������B
�V���K�[���Ƃ����Ζ��ʂɂƂǂ܂炸�A�ʼn�A����A�lj�A�X�e���h�O���X�Ƒ��W�������ɋy�Ԃ��A����̂S�P�W�̍�i�͂ƃV���K�[���Ƃ��̉Ƒ������������������̂��܂ޖ��ʂ݂̂̓W���������B
������ɖڂɗ��܂����̂͂R�O�ˍ��̍�i�A������݂̂׃��v�B�p���Ńt�H�[�r�Y���C�L���r�Y������̉e��������̊G�ł���A���̌�̃V���K�[��������Â���敗�ւ̑O�t�ȂƂ����������ň�ۂɎc�����B
|
|
| 2002�N�@�@�@�@�@�@�@�@ |
�������m���p�� |
�v���h���p�ٓW
�v���h���p�ق�16�A17���I�𒆐S�Ƃ��郔�F�l�c�B�A�ƃt�����h���G��̏d�v�Ȏ��W�ɂ���Ēm���Ă��邪�A�����ꂽ��ƂɊ���̏��^���A�L�ĂȔ��p�i���W�ɏ�M�����������n�v�X�u���O�ƃu���{���̓�̃X�y�C�����Ƃɂ��Ƃ��낪�傫���B
����͎����i�̂����A�x���X�P�X��5��i�A�S����6��i���͂��߁A�G���E�O���R�A�X���o�����A�����[�����A�e�B�c�B�A�[�m�A�e�B���g���b�g�A���[�x���X�A���@���E�_�C�N�Ȃǂ̌v77��i���ꓰ�ɓW������Ă���B
�����̂��Ƃ����A�����̍�i�̓W���͒��J�Ɍ��悤�Ƃ���Ɣ������Ō��lj����c��Ȃ����Ƃ������B���͂����ʂ�A������ƌ���Ƃ����Ă������ł̓W����͓���҂������̂ŁA���̂�����Ƃ����X�v���ɔC���Ȃ��̂ōŏ��͗���ɏ���āA�ł�������ƋC���ď�������A�C�ɂȂ���̂������ēx����Ƃ����A���ԂɂƂ������s�V�悳����͂���������E�����������Ȍ������������B�܂��l�������������킯�ł͂Ȃ��B�l�̓��̌�납��A�w�L�т��Č��Ԃ��������茩���Ē������̂����炨�����肢�����B |
 |
����ۂɂ̂�������i�̊G�t�����w�������B
�@���[�������F�����߂̌�h��
�@�S���F���P

|
|
2002�N
|
���s�����ߑ���p�� |
�J���f���X�L�[�W

���ە\���̐��ҁA�J���f���X�L�[�̒��ۂւ̓���`���悤�Ƃ���W����B
�@���A�������w�J���f���X�L�[����Ƃ�ڎw���̂͂P�W�X�U�N�A�R�O�̂���A�x���o�����B��ړW�ł͂��肪���̏����̏K�삩��W������Ă������A�G����̓t�H�[�r�Y���̉e�������邪�������o�������̂ł͂Ȃ��B
�~�n�����}���钛���͒E�Ώۉ��̎��݂�͍��A��Ώ̂̕\����`���l������P�X�P�O�N��ȍ~�̂��Ƃ��B���̌�̃R���|�W�V�����`�`�Ƃ�������i����͉��y���͂��ߑO�q�I���|�p�ƘA������l����悵�Ă���B
���ە\����`�̑n�n�҂Ƃ��Ċ���A���X�N���ɂ����āA����Ƀh�C�c�̃o�E�n�E�X�ɂ����Č�i�̎w�����s���Ă���B
���ۂ̎��ォ��̍�i�́A���̍\�}�ɂ����Ă��F�ʂɂ����Ă��������|��������ŁA�ǂ�Ȍ��t�������Ă��Ă����z�Ȃǂ������Ȃ��Ƃ����������B���㉹�y�ɒʂ��鉽�����A�S�������������������Ă���Ƃ��������Ȃ��B
�ǖʂ����ς��̍�i(�R���|�W�V�����Y�ƃR���|�W�V�����Z�͈����������B
Wassily Kandinsky �i�P�W�U�U�|�P�X�S�S�j�@���V�A�@���ە\����`
|
|
���g���|���^�����p�ٓW

�j���[���[�N�̃��g���|���^�����p�فA�ߑ���p����̃R���N�V��������A20���I�O���Ɋ�����Ƃ̑I�肷����ꂽ��i72�_���W������Ă���Ƃ����̂ŁA�������ɊJ�Â���Ă���僌���u�����g�W�Ƃ��킹�Ĉ�C�Ɍ��悤�Ƃ����킯�ŁA�����̎O�l�ŏH�̋��s��K�ꂽ�B
�s�J�\�A�}�e�B�X�̗������̖�����͂��߁A���f�B���A�[�j�A�{�i�[���A�o���e���X��̍�i���A����N������ƂɁA�V�̃Z�N�V�����ɕ����W������Ă����B
�V�̂r�d�b�s�g�n�m
�@�T�P�X���I����Q�O���I�ց@ �U�t�H�[���̉�Ƃ����@�@�V�L���r�X���̉�Ƃ����@�@�W�`���ƕϊv
�@�X�P�X�Q�O�N��@�@�@�@�@�@�@�@�@�Y1�X�R�O�N��@�@�@�@�@�@�@�Z�G�s���[�O
��������̉�Ƃ��ꓰ�ɉ�����̂����̎��̊ӏܖ@�́A�S�̂�������ƌ��Ă���S�ɐG�ꂽ���̂�������߂肵�Ă������ӏ܂���B���J�Ɍ����Ƃ���œ��̒��ł�������ɂȂ��āA�������ڂ����邾���Ƃ����C�����邩�炾�B�����ꏏ�̎O�l�������ł͂��Ƃ����̂������ʂ�B
�ꎺ�ڂ��s�J�\�́@�u�Ӑl�̐H���v�ɖڂ��Ƃ܂����B����͂��̓W�����������Ă��邩��킩��₷�����Ƃ�����悸�̓s�J�\�����ǂ����B�u�������̏��v�ɂ̓u���a�X�g�����p�قɂ������Ԃ��^�C�c�̃A�����J���Əd�Ȃ���̂����苻���[���ӏ܂����B�L���r�Y���̃s�J�\�͎��̍D�݂ł͂Ȃ��̂����̎��ケ�낪�����Ƃ��炽�߂Ďv�����B
�s�J�\�Ƌ��ɂQ�O���I�̔��p�v���Ƃ������ׂ��L���r�Y���ݏo������ƁA�W�����W���E�u���b�N
���͂ǂ��炩�Ƃ�����Ƃ��̐Â��������[���A�n���������C���̂悤�ȂƂł����������悤�Ȗ��킢�̃u���b�N���D���������B��������_�o�Ă��肻�̒��Łu�C�[�[���Ɍ������č��鏗�v�̐F�ʂ��C�ɓ������B
|
|
�C�ɓ�������i�̊G�t�������B
�s�J�\�F�u�A�����J���v�@�u�Ӑl�̐H���v�@�u�������̏��v�@�@�A�����E���\�[�F�u���C�I���̐H���v�@
�u���b�N�F�C�[�[���Ɍ������č��鏗�@�@�A���h���E�h�����u�e�[�u���v�@
|
|
�僌���u�����g�W
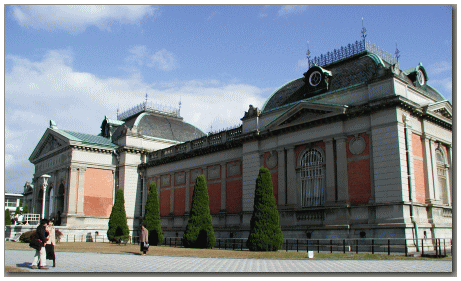
�Ǝ��̖��Õ\������u���Ɖe�̉�Ɓv�Ƃ��Ēm����A17���I�I�����_�̋��������u�����g�E�t�@���E���C��(1606-69)�̓W����B
�����u�����g�Ƃ����A�W�c�ё���Ƃ�����u�e�����v���m�̉�U�w�u�`�v��u��x�v���v���o���̂�������W���̑��͉�Ƃ̏[�����P�U�R�U�N����̖����������ڂ�ׂ����T���\���ŁA�����u�����g�����h���Ă�܂Ȃ��������[�x���X��f�i�Ƃ������i�ł������B
�Ƃ��ɑ��������̂��o�ςɂ��[�����A�ё���ƂƂ��ĉ~�n�����}��������̍�i�B�����͈ߑ��̍ז��ȕ`�ʕ\���Ƃ����A���̕\���͂̂������ɂ͖ڂ����������Ƃ͂����A���ׂĂɂ����Ē�����ɂƂ��Ă̖����̂������̂Ƃ������������Čl�I�ɂ͂������͂������Ȃ������B
�ё���ŗD��Ă���Ǝv�����͉̂�Ǝ��g�̓��ʂ̏o�����摜�������B�A����͎Ⴋ���A���C�f���ŕ`�����u�Ă��������摜�v����ӔN�́u�����摜�v�܂Ő���������A���摜��ǂ����ƂŁA�O���̖��Âɂ�錀�I�Ȃ��̂���[�����_�I�Ȃ��̂ւƍ앗�̕ϑJ�����ĂƂ邱�Ƃ��ł���B
�����Ŗ��͓I�Ȃ̂͗c�����琬�l����܂ł̑��q�e�B�g�X��`������i�����̑O�̃e�B�g�D�X�͉E��Ƀy���A����ɃC���N��������A������[���l���Ȃ���Ȃ�Ȃ���҂̓��ʂ�������悤�ȍ�i�ƂȂ��Ă��ĂƂ��ɍD�������Ă��B�`���ꂽ�\��ɑ��q�������Ƃ̈��������B
��\��Ǝv����u��x�v�����ɂ��āA�o�ϓI�ɂ͓]���̈�r�����ǂ�悤������Ƃ͂܂��܂��[���P�U�S�U�N�ɕ`���ꂽ�Ƃ����`���ꂽ�z���ƃJ�[�e���̂��鐹�Ƒ��̓o���b�N�Ɠ��̂��܂��G�I���ʂ��������ꂽ�����[����i�ŃJ�[�e���̌������ɓW�J����h���}���L�������Ȃ�悤�ȊG�ł������B
�o�ϓI�ɂ͔j�Y���o��������Ƃ̔ӔN�̍앗�͏_�炩�����̂ւƕω��B�P�U�U�T�N��̓��X�ƈЌ��ɖ��������m�\���f���炵�������B
����̓����u�����g�̂�����̎d���A��ʼn棂����҂��Ă����̂������G���肾�����̂͂�����Ɗ��ҊO�ꂾ��������Ƃ̐��U�ɂ킽���Ƃ��_�Ԍ��邱�Ƃ��ł����B
|

���̑O�̃e�B�g�D�X
�@ |
��
�}�����b�^�����p�ٓW
�}�����b�^�����p�ق̏�����i���A���{�ł͏����J�ƂȂ郋�A�[���E�R���N�V��������I�肷������40�_�𒆐S�ɁA���l�A�����]�A�R���[�A�u�[�_���A���m���[����̊G���i�v80�_���Љ�
�W���̂S�������l�A�S���������]�Ƃ����W��������B
�ȑO����A���͂ǂ������킯�����@�Ƃ����l�C�̍������l�̍�i�ɂ̓s���Ɨ�����̂��Ȃ��̂����A���@�ȊO�A���Ƃ��I���Z�[�ɂ�����P�̏��ȂǂɂЂ����B����̓W���̒��ł̓|�[��-���B�G�̃Z�[�k�삪�悩�����B����������̂͂͂��߂Ă������A������Ƃ̃����]�̊G���y���B���ł��u���摜�v�ɒm�I�ȕ\��A��Ƃ炵���������������悩�����B |

�����]�̎��摜
|
�A���h�����[�E���C�G�X���ʑf�`�W
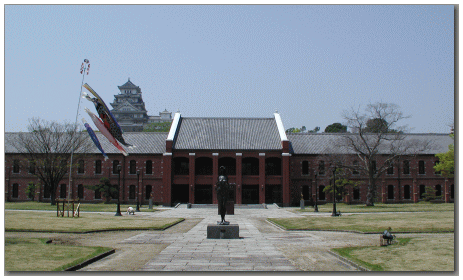
���C�G�X�Ƃ̏o��͂P�X�X�O�N�ɑ��Ō����e���y�������Ƃ���A�u���C�G�X�W�w���K�v�������B
����́u�I���\���V���[�Y�v�Ƃ�����A���ʑf�`�W�ŁA�h��ȍ�i�͊F���������e�̔Z�����̂ł������B�Q�Q����A�R�O�N�Ԃɂ킽��I���\���Ƃ̏Z�l�A�o�̃N���X�e�B�[�i�ƒ�̃A�����@���Ƃ̐[���𗬂̒��ŕ`���ꂽ���̂ŁA�Z�܂��A�n�E�X����芪�����R�A�[���C���⍒���܁A�ȂǃI���\���n�E�X�̏ё��Ƃ����Ă�������i�Q���B�����āA��\��ƂȂ����u�N���X�e�B�[�i�̐��E�v�Ɍ����Ă̏K��̐��X�ɋ����B�ޏ��̌��p�A���x���J��Ԃ��`���ꂽ�u���ꂽ��̃f�b�T���B���̈����N���X�e�B�[�i�̎�̕\��̑厖���ɉ�Ƃ͔[���̂����܂ŌJ��Ԃ����g��ł���̂��B
���̃R���N�V�����̓����̓��C�G�X���g���u�t�F���V���O�̂悤�ɁA�ˌ��̂悤�ɑΏۂƂ̊ԂɋN���鋭����ہv��\�������̂��ƌ����Ă���悤�ɁA���̎����̏ꏊ�ł����������Ȃ����I�ȐS�̓����A�M�ӂ₽���܂肪���ڎ��ɕ\������Ă���Ƃ���ɂ���B�f�`�Ȃ�ł͂̃V���v���ł͂��邪�����������邱�Ƃ̂ł����i�Q�������B
|
�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@ |
| 2004�N |
�������m���p�� |
�}�}�`�X�W
�}�`�X�P�Ƃ̓W���������̂͂P�X�X�P�N�ȗ�������P�T�N�Ԃ�Ƃ������ƂɂȂ�B
�u���@���G�[�V�����v�Ɓu�v���Z�X�v�Ƃ������_����A�}�e�B�X�̍�i�����Ă������Ƃ����W�����@���V�N�������B�}�`�X�̍�i�͈ꌩ�Ȃ�ł��Ȃ��Ђ��ꂽ�悤�Ɍ������������ɕς�鉽�����Ȃ��Ǝv���邦��тʂ��ꂽ�`��ł���A����ȉ�Ƃ̍l������A����ߒ��ɏœ_�Ă��W����͂�����i����ׂ������Ƃ͈���ċ����Ԃ������邱�Ƃ��ł����B
���ɂ͓��������قȂ�\���ŕ`����������i��A����r��̎ʐ^�Ɗ�����A�Ȃǂ��W������A���傤�Ǔ��َ҂�Ώۂɂ����w�|���̍u�����J����Ă��ėL�Ӌ`�Ȏ����߂������B
Matisse, Henri�@�i1869-1954�j�@�@�t�����X�@�@�t�H���B�X�g(��b�h�j
|
|
�Q�l�����F�W����}�^
|
![]()