2月28日
2月は逃げるようにいってしまう。その最終日、やっと雨があがり、晴れ間が見えた。
薄日の差す中をユキワリイチゲを探しにいった。
いつもの群生地ではまだまだ蕾であと10日はかかりそうだったが・・・

道路わきの陽だまりで少し控えめに咲いているのを見つけた。


あまりにも薄い色合いだ。
ルリイチゲというにふさわしいあの青紫になるにはまだまだ日照不足のようだ。
〜〜2月の手仕事〜〜
原毛を染めて紡ぐといったことに夢中になったことがあった。
衣装缶にその糸が詰まっている。なんとか形にしなきゃ〜〜
というわけででマフラーを織った。
紡毛糸は縮絨が必要なので写真にとったがこれはまだ途中
湯をかけながら踏んだり、たたいたりの面倒な作業が残っている。
水場での作業はあたたかくなってからやるとしてあと数枚は織りたいとおもっている。
気の長い話だが秋までにできればいい〜〜生地がしまって独特のやさしい風合いが出るはず。

2月25日
一雨ごとに〜〜もう春なのか〜〜
今週はよく降る。冬中咲いていた吊り鉢のナデシコに水滴がいっぱいついた。
凍てつくような冬があってこそ春の到来もうれしいというものだが
年々、温暖化を肌で感じるようになってきた。
今年の瀬戸内は何となく物足りなさがのこる。

2月21日
早春の花を求めて県北へ行った。
先ずはユキワリイチゲを探した。まだまだ蕾は硬くあと10日はかかりそうだった。
先週からの冷え込みで、林の樹下には雪が残っている。
こんなに冷たくてはオウレンは咲いているのだろうか。

暗い林縁でじっと目を凝らした。目がなれると見えてきた・・・
2週間前にはまだ頭を出したばかりだったセリバオウレンがあちこちで開花していた。
(拡大×4〜5)

二週間前にはまだ硬かった梅もほころび

そして、セツブンソウの群生地へも行ってみると、
可憐な花が緩やかな斜面を埋め尽くしていた。見事な群生地だ。



2月18日
〜今朝のおめざ〜
今、近隣のデパートでは「おめざフェア―」と銘うって朝のTV番組で紹介されたお菓子などが紹介されている。
私は手づくり”おめざ”
家で焼く菓子は簡単が一番。材料を混ぜて焼くだけのアップルケーキは我が家の定番。

2月15日
播磨路へ

2月12日
窓辺でカタバミがゆれている。
冬のカタバミ、縮こまった花に比べ紅葉した葉が美しい。
午前中は開き、夕方になると徐々に閉じる。特に閉じかけた頃がいい。
儚げなのがいい。
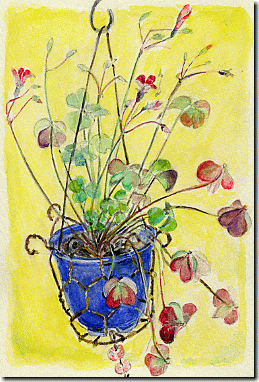
2月9日
今年に入ってからなるべくお菓子は自家製を心がけている。
量はいらない・・・というわけで最近はもっぱら小さなオーブントースターで作れる範囲のもの
をこまめに作ろうと決めた。パイ風にすれば、林檎ケーキだって可能だし
マロンのタルトだって、スイートポテトだってできるのだ。
今日は、クッキーを焼いた。

プレーン・庭のローズマリーを入れたハーブクッキー・レーズン&クルミ入り。
さくっと美味しく出来た (^o^)丿
2月7日
薄ぐもりだったが風もなく坂道を登ると汗ばむほどのあたたかさ
そろそろ、セリバオウレンが咲き始めたかもしれないと県北へ出かけた。







