秋篠寺〜西大寺〜菅原神社〜喜光寺〜垂仁天皇陵〜唐招提寺〜薬師寺
5月21日(金)
天気:晴れ
季節はずれの台風が近づき大雨をもたらした翌日
以前から訪ねてみたかった秋篠寺を出発点とし多くの天平文化に出会える西ノ京を歩いた
START 10:00 〜 FINISH 17:00
奈良 2
秋篠寺〜西大寺〜菅原神社〜喜光寺〜垂仁天皇陵〜唐招提寺〜薬師寺
5月21日(金)
天気:晴れ
![]()
![]()
季節はずれの台風が近づき大雨をもたらした翌日
以前から訪ねてみたかった秋篠寺を出発点とし多くの天平文化に出会える西ノ京を歩いた
START 10:00 〜 FINISH 17:00
| 大和西大寺駅(近鉄)10:00―歩20分―10:20秋篠寺10:40―歩20分―11:00西大寺12:00―昼食― 13:10―歩20分―13:30菅原神社・喜光寺・菅原はにわ窯公園14:30―歩15分―垂仁天皇陵―歩15分― 15:00唐招提寺15:50―歩10分―16:00薬師寺16:45―がんこ一徹長屋―17:00西ノ京駅(近鉄) |
 |
| 奈良時代末期776年に光仁天皇の勅願により薬師如来を本尊として僧正善珠大徳が開き、 その造営は桓武天皇に引き継がれ平安遷都と時を同じくして伽藍の完成をみた。 その後、真言密教道場として隆盛を極めたが1135年兵火で金堂、東西両塔など主要伽藍を焼失。 その面影は今も林中に点在する礎石でしのぶことができる。 明るい境内の真中に堂々と建つ現在の本堂は当初講堂として建立されたが鎌倉期に大修理を受け(再建ともいわれる)以来本堂と呼ばれている。様式的には奈良時代建築の様式で単純、素朴な中に均整と落ちつきをみせている。 境内にはこの他、大元堂、開山堂などがある。 |
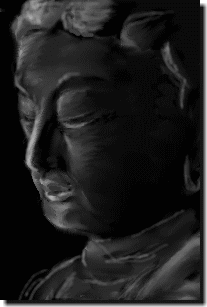
| 765年(天平神護元年)称徳天皇の発願により東大寺に対する西の大寺として創建された。 鎮護国家と平和祈願のため金銅四天王像を本尊とした。当時は110もの大伽藍を誇ったが度重なる火災で衰退、 鎌倉時代になって叡尊により再興、真言律宗の根本道場として整備された。 室町時代に再度、兵火に見舞われ、現在の建物は江戸時代に再建されたもの。 本堂前の塔の基壇に当時の規模がうかがえる。 |
 |
近鉄線を越え300メートル先を右折、右へカーブすると 西大寺奥の院 鎌倉時代、西大寺を再興した叡尊の立派な墓 |
| 東塔跡の基壇と本堂 本堂の主な仏様は本尊釈迦如来立像、 文殊菩薩騎獅像と四侍者像 印象に残ったのは四侍者像のうち最勝老人と善財童子 特に童子の赤い目は灰谷健次郎さんの小説「兎の眼」 に「あいかわらず善財童子は美しい目をしていた。 人の目というより兎の眼だった。 それはいのりをこめたように 物を思うかのように静かな光をたたえて美しかった」 として登場する目で興味深く拝見した。 |
 |
 |
大茶会 中興の祖、叡尊が1239年正月、密教の修法を行い万民豊楽を祈願した時、その結願を八幡宮に献茶し、そのあまりを集まった人々に賞味させたのが西大寺大茶会のはじまりと説明している。 |
愛染堂 本尊愛染明王は秘仏のため見ることはできなかったが1247年に叡尊の発願により仏師善円がつくった鎌倉期の代表的木造彩色像で高さはわずか34センチ。その摸刻から緻密な彫法をうかがえる。 また、興正菩薩叡尊坐像は80歳の叡尊の意志の強そうな個性がうかがえる写実的な像で気迫を感じた。 |
|
聚宝館 奈良時代、鎌倉時代の仏教美術を中心の寺宝展 仏像では平安時代初期の唐様の吉祥天像が穏やかな感じでいいなとおもった。 また、密教法具、国宝の金銅宝塔は細密なつくりで美しかった。 |
|
| 四王堂 堂内に入ると圧倒されるほどに大きい 長谷寺式十一面観音立像が右手に錫杖、左手に華瓶を捧げて立っている。この像は円心作の藤原彫刻で 1289年、京都から移されたもの 西大寺創建のきっかけとなった四天王像は 再三の災禍にかかり再興されたが 増長天が踏まえる土の邪鬼は創建当初の物 覗き込むようにしてその邪鬼を見るとなんともこっけいな顔立ちで親しみが持てた。 |
 |