碓氷峠入口

峠入り口に立ったのは9時30分。峠まで3.3キロの登り。峠までの旧中山道は消滅しているので遊歩道を歩くことになる。はじめは車道から・・・

5分も歩くと車道と分かれ遊歩道へ。クマ除けの鈴と、そろそろヤマヒルのでる季節だというのでここで虫よけ、ヒル除けスプレーを足首にかける。

突然、リスに出会ったりしながら、川のせせらぎも聞きながら気持ちよく歩く。

分かれ道にも道しるべがしっかりしているので安心。ここは右の道を行く。

出発より20分ほど歩いた頃、吊橋を渡る。


細い山道を行く。木漏れ日がうつくしい。

15分くらい歩いた頃、歩道橋があらわれ、これを渡って車道と交差、再び山道に入る。


20分ほど歩いただろうか。行く手にT字路の標が見えてくる。右に行くと見晴らし台。
左に行くと熊野皇大神社と書かれている。

先ずは見晴らし台へ石畳道を進む。
「見晴らし台到着」
10:45・・・思ったより早く登れた。峠でゆっくりすごそう。

案内板によると、左手下方に関東平野、正面に上毛三山(妙義、榛名、赤城)右方に浅間山、そして遠く南北アルプスや時には富士山まで見えるとある。
関東平野は霞んで僅かにしか見えなかったが、正面の妙義山の特異な山稜が美しかった。眼前の山並みに感動。

浅間山

広場の中心には群馬県と長野県の県境モニュメント。石が並んでいて印象的。

見晴らし台には、インドのノーベル賞詩人、タゴールの像や、万葉歌の歌碑もあった。
ゆったり山々を眺めた後、熊野皇大神社へと向かう。
その前に神社前の力餅屋、しげの屋へ。きな粉の力餅とおそばを注文する。
力餅は伸びがあってとても美味。

「熊野皇大神社」
その昔、碓井権現(熊野権現)といわれた神社は群馬と長野の県境に位置する。神社に残る古鐘は鎌倉時代に松井田一結衆によって寄進されてもので、境内には三本社があり、
中央の本社は県境上にある。
石段にかぶさる緑の美しい鳥居の前に立った。手前の石灯篭に「安政遠足決勝点」の文字が見える。安中宿の武家屋敷をスタート点として全長約30km。標高差1050mを駆け抜ける侍マラソンの終点はここだったのだ。ついひと月前に今年も催されたに違いないマラソン。何人くらいが完走したんだろう・・・。


賽銭箱がふたつ並んでいる。峠の神社らしく県境に立っているので、
長野県側(ひだり)を熊野皇大神社。群馬県側(みぎ)を熊野神社というそうで、
したがって賽銭箱も二つあるということらしい。両方にお供えして手を合わせる・・・。
シナノキ。パワースポットだそうです

峠を下る(旧中山道)
12:00~


思婦石や小さな祠などを見ながら下っていく。最初の分かれ道を右へ。

またもや分かれ道があるが要所要所に標識が立っているので迷うことなく歩ける。
それに加え、安政遠足の道案内の標が安心感を与えてくれ嬉しい。
長坂道。

どんどん険しくなり両側から迫ってくるような道を下っていく。よく晴れていて明るいのが助かる。
途中、道を隔てる流れ。乗る石を選んで滑らないように通過する。

笹沢
人馬が休む家があったという「人馬施行所跡の木札」とか、峠へ登る旅人がその水で姿形を直し、のどを潤したという水場「化粧水跡」といった木札が立っている。
しばらくいくと、倒木が道をふさぐような所も。
 子持山
子持山・・・一帯をそういうらしい。
陣馬が原 12:30
下りだして30分。少し広い場所に出る。古戦場だったらしい。
新田と足利のうすい峠合戦、武田と上杉のうすい峠合戦が行われたという。

ふりかえって写真を撮ると、来た道は左側。右は和の宮道(安政遠足の道)
坂本へは手前に進む。陣馬が原の先は狭い道が続く。

途中「一つ家跡」の立て札。
「ここに老婆がいて旅人を苦しめた」と書かれていた。
山中坂

この下にある山中茶屋から通過してきた陣馬が原への急登を山中坂というらしい。
登りの厳しさは下りながらも伝わってくる。
山中学校跡
 山中茶屋
山中茶屋

寛文2年には13軒の立場茶屋ができ、寺もあって、茶屋本陣には上段の間が2カ所あった。明治の頃には小学校もできたなど解説されている。
入道くぼ

ここからは赤土の下り。
杉の木立がつづく。見つめると吸い込まれそうな美しさだ。

杉木立を抜け景色が広がった所。一息つく。

 栗が原
栗が原

明治天皇の巡幸道(廃道)と中山道の分岐点。
明治8年、群馬県最初の「見回り方駐屯所」があった。
座頭ころがし

急坂、滑りやすく危険な坂が10分ばかり続く。


「一里塚」とかかれた木札が立っている。その辺りから登ると慶長以前の旧道があり、その途中に小山を切り開いた一里塚があるという。この辺りで「座頭ころがし」はおわり。
道を挟むような土手にコアジサイが美しい。


北向き馬頭観音と南向き馬頭観音


上から旅人を見守っているかのよう。
掘りきり

秀吉の小田原攻めで北陸・信州軍を松井田城主が防戦しようとしたところらしい。狭い道の両側が掘りきられている.こんな短い距離で防戦できたのかと不思議・・・。
だらだらと山道は続く。途中、美しいさえずりはキビタキだ。

やがて東屋が見えてくる。後2.5キロで坂本宿だ。

「碓氷峠の関所跡」
「刎石茶屋跡」の立て札と今なお残る石垣などを目にして下っていく

少し入った所に「弘法の井戸」がある。今も水が出ていたが、野生動物の水飲み場でもあるのかクマ注意など書かれている。

馬頭観音石碑

そして、「
覗」
坂本宿を見下ろせる。一茶は「坂元や袂の下の夕ひばり」と詠んだ。とある。

最後に、厳しい石の道。「坂本からの峠越えは覗までが厳しい」と案内本には書かれていた。登りはさぞ厳しかろうが下りもまた歩きにくく足に堪える。

刎石坂・・・溶岩節理の岩石がゴロゴロ。

柱状節理

やがて落ち葉と石の混じったような道となり、番所やぶりを取り締まった「堂峯番所」の立て札をみて、石垣上に構えられたという番所を想像しながら進む。
木で階段状になった道を下ると・・・
いきなり前方が開け、峠越えは終了。14時50分

左わきにあった東屋でおにぎりを食べ、しばし休憩する。
前の国道を車が行きかう。ツーリングの男性にもあい言葉を交わす。
国道18号を坂本宿方向へ歩く。
この日は宿の最寄り駅、横川駅までの予定。

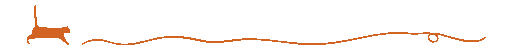


![]()