安中から板鼻へ
2019年4月20日午後
北陸新幹線高崎駅から信越本線に乗継ぎ、安中についたのはすでに13時30分を回っていた。先ずはこの日の出発点と決めた安中宿の西口へ向かった。「史跡、安中大木戸跡」は安中上野尻郵便局の敷地内にあった。

旧中山道は県道125号に当たる。古い町並みではあるが往時をしのばせるものは少ない。

★有田屋と便覧舎
200mほど行くと古い蔵と大きな暖簾の店舗があった。天保3年創業の醤油醸造の老舗、有田屋だ。その向かいには「便覧舎址」と刻まれた碑がたっている。

 建物は明治の大火で残っていないが、解説によると便覧舎は、明治5年に有田屋当主湯浅次郎によって創設された日本初の私設図書館で、和、漢、洋の書物3000冊の蔵書があり、だれでも自由に無料で閲覧できたということだ。 建物は明治の大火で残っていないが、解説によると便覧舎は、明治5年に有田屋当主湯浅次郎によって創設された日本初の私設図書館で、和、漢、洋の書物3000冊の蔵書があり、だれでも自由に無料で閲覧できたということだ。
通りの北側が安中城を中心に武家屋敷が並んでいた地域だというので通りを左折して向かった。安中城は1559年に安中忠正が築城、その後信玄によって落城するが慶長19年(1614)井伊直勝によって再建され城下町として整備されるも明治維新後取り壊され現存するものはないという。跡地は安中小学校になっている。
当時を語るものとしては城の南西部を走っている大名小路に面して、重厚な地方武家屋敷の造りを今に残す郡奉行役宅と復元された武家長屋(四軒長屋)がある。
★郡奉行役宅 長屋門を入ると管理人さんが迎えてくれ詳しく解説してくれた。 長屋門を入ると管理人さんが迎えてくれ詳しく解説してくれた。
母屋は群馬では珍しい曲がり屋構造であること、母屋の間取りは十畳の座敷を中心に納戸やお勝手台所を拝し、北側に上段の間と式台つきの玄関が配置されているなど。
当時のままの梁や天井の木組み、引き戸についた障子など興味深く拝見。近年、葺き替えられたという屋根が美しかった。
★武家長屋 藩は3万石の小藩だったため、30人ほどの上級武士以外の藩士はこのような長屋に住んで前庭で畑を耕すといったつつましい暮らしぶりだったようで、この長屋も上座敷と下座敷と二間からなる狭いものであったようだ。 藩は3万石の小藩だったため、30人ほどの上級武士以外の藩士はこのような長屋に住んで前庭で畑を耕すといったつつましい暮らしぶりだったようで、この長屋も上座敷と下座敷と二間からなる狭いものであったようだ。
当時をしのばせる二つの建物を見た後、大名小路をたどると枝垂れ桜の美しい一角があった。
★安中教会
県下初の教会だったという安中教会。その礼拝堂は新島襄召天30周年を記念の建築だということだ。

安中と新島襄
新島襄は、天保14年(1843年)、安中藩士の子として江戸・神田に生まれ、21歳で渡米しキリスト教徒となり、帰国後父母の住む安中へ帰郷、僅かな滞在中にキリスト教を広めたのだとか。
★須藤本陣跡
大名小路を旧碓氷郡役所まで歩き、右折、大手坂を下ると中山道の伝馬町信号へ戻る。
安中郵便局の敷地内に碑が立っていた。

★熊野神社
安中城鬼門の守護神、総鎮守として歴代藩主に崇敬されたという。境内には樹齢1000年という大欅がそびえる。
★安政遠足(遠足)
街道のいたるところに立っていた幟。一体なんだろうと思って調べてみた。
安政遠足の文字が染められている。「あんせいとおあし」とは1855年、藩主板倉勝明が藩士の鍛錬のために安中城門から碓氷峠の熊野権現神社まで走らせた徒歩競争。この遠足は日本におけるマラソンの発祥となったと言われる。
昭和50年から保存会、安中市主催で毎年5月第二日曜にサムライマラソンが催されるようだ。

★久芳橋
安中宿を後に国道18号へ出て、久芳橋を渡る。下を流れるのは碓氷川。遠くに上毛三山の妙義山だろうか。山がうっすらと見える。

安中駅前を通過。碓氷川堤の方向へ。堤に合した角に馬頭観音の石碑があり、
その先で「安中宿1.2㎞、板鼻宿1.2㎞」と書かれた丸太道標を見つける。二つの宿の中間ということだ。この辺り、道標が少ないのでわかりにくかったがホッとする。
★300mほど先に1802年建立の庚申塔道標。この辺りを中宿という。
 右に曲がると「中宿糸繰燈篭人形展示館」があるがあいにくしまっていた。中宿に伝わる農民芸能で人形の胴に灯りを入れ糸で操るのだということだが見てみたかった・・・。 右に曲がると「中宿糸繰燈篭人形展示館」があるがあいにくしまっていた。中宿に伝わる農民芸能で人形の胴に灯りを入れ糸で操るのだということだが見てみたかった・・・。
★板鼻宿渡し場跡へと通じる丸太道標が、ポツンと建ってはいたが,その渡しは今は見当たらない。
往時は渡し場に茶屋があり、夏は徒歩渡し、冬は仮橋で渡ったようだ。
現在は鷹之巣橋で渡る。その先、道は大きく右へまわる。
★板鼻宿へ(県道137)

★板鼻堰用水路 江戸時代初期(1604~14)に稲作振興と宿場用水として作られた。
鷹巣山麓の堰口から碓氷、九十九両川の水を取り入れ烏川にそそぐ15キロの用水路。
英泉の浮世絵にも描かれている。

★板鼻本陣跡
 現在は公民館のたつ裏手に皇女和の宮が宿泊したという書院が残っている。土曜日ということで休館していた。 現在は公民館のたつ裏手に皇女和の宮が宿泊したという書院が残っている。土曜日ということで休館していた。
★双体道祖神
1792年のもので、台座には京都、江戸、日光、善光寺などへの道程が刻まれているようだ。
 板鼻下町で道は国道18と合流。 板鼻下町で道は国道18と合流。
★寒念仏橋供養塔
解説板要約。板鼻宿の念仏講中が寒念仏供養によって得た報謝金をたくわえ1732年石橋を改修、旅人の利便に供した。その後、破損したので1802年には宿本陣の当主,木嶋七郎左衛門がさらに堅固な石橋に改修、近くに供養記念塔を建て後世にのこした。

★上野国一社八幡宮への道 左に曲った所に巨大な赤い鳥居が立っていた。

この先、少林寺入り口信号を左折し、群馬八幡駅へ向かう。本日終了(17:20)

この日の宿泊地、二駅先の高崎へと戻る。

広重の版画より「案仲」
宿場の中にこの風景に当たるところはなかった。道は西に向かって上り坂になっている。
さらに西に向かった郷原村辺りだろうということだ。

英泉の版画より 「板鼻」
板鼻宿の江戸口付近と思われている。
橋は宿の念仏供養2万日を達成記念に古い石橋を改装した「寒念仏橋」
この橋は後に訛って「寒熱橋」といわれた。

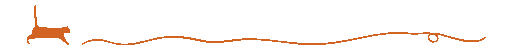
 
|
|
![]()