本山~洗馬~塩尻

(東から西)
2018年11月2日
塩尻駅についたのは12時前。洗馬への出発点である下大門交差点へ向かう。
四差路になっている交差点を県道305号に入りるとすぐに大門神社がある。この神社境内からは日本最北の弥生銅鉾が見つかっている。

すぐ隣に黒い格子で囲まれた中にたくさんのお椀が奉納された耳塚神社がある。天文17年の桔梗ヶ原合戦で武田晴信と小笠原長時が激突。討ち死にした将兵の耳が葬られたと伝わっている。

道はひたすら西へと向かっている。
中央本線のガードをくぐったあたりから遠くに穂高を望む。この辺りではブドウ栽培が盛んなようだ

昭和電工を右に見て進むと、両塚の残る平出一里塚
南塚の塚木は信玄の軍師、山本勘助が赤子を拾ったという伝説があり「勘助子育ての松」と呼ば
れ、その松葉を煎じて飲むと乳の出がよくなると言われ「乳松」もよばれるのだとか。

周辺にブドウ畑の広がる県道を行くと
縄文から古墳時代、平安時代にかけての大集落跡「平出遺跡」があり、復元住居が点在している

↑縄文時代の村 ・↓古墳時代の村

北アルプスの山々が望める広大な草原で当時の人々ののびやかな暮らしが想像される。中を覗いてみると、囲炉裏からかまどへと進化した様子や、梁が付けられるようになった様子がうかがえ、ゆるやかな進化を遂げていく村の生活がみえてくる。
中央本線の踏切の先に長野県野菜花き試験場がある。周辺にはそば畑もあり試験場の人たちが作業している。少し立ち話。野菜、果物、養鶏、など多分野にわたるようだ。


佐久平ではリンゴ畑が広がっていたが、こちら、松本平はブドウ栽培が盛んなようだ。近くにワイナリーもあった。
中山道一里塚交差点で左折し少し旧道に入りさらに国道19に合流。(13:40)

途中、旧道に入りさらに交差点で県道304に入る。中山道の標識があるからこそ歩ける。
細川幽斎が歌を詠んだという肘懸松。ここで詠んだと伝えられる歌は
「肱懸けて しばし憩える松陰に たもと涼しく 通う河風」
何代目かなんだろう。ひじがかけられるほどの大きさでもなかった。

松の先、右手の細い下り坂を下り枡形状に進むと右角に分去れ常夜燈があり善光寺西街道追分

少し行くと分去れ道標がある。ふりかえってみると、「右中山道左北国往還善光寺道」と刻まれている。

~洗馬宿~
邂逅(あうた)の清水
木曽義仲の家臣、今井四朗兼平が疲弊した義仲の馬の足を洗って元気を取り戻させたという清水。洗馬の地名はこの故事に由来している。

洗馬宿は慶長9年(1614)中山道が塩尻峠経由に付け替えられた際に塩尻宿、本山宿と共に新設された宿で、北国往還善光寺道の追分に当たるので大いににぎわい、北陸の鮭や鰤を煮込んだ「洗馬煮」が名物だったという。幕末の家数150軒、大きな旅篭を持っていた。しかし、宿は鉄道開通に伴って名園と言われた本陣、脇本陣の庭は駅の敷地となり、また昭和7年の大火で宿並は廃墟となったという。
街道筋にも宿の面影を残す建物はなかったが、そこはかとなく街道の趣きが残っている。
 本陣跡、脇本陣跡、荷物貫目改所跡 本陣跡、脇本陣跡、荷物貫目改所跡 芭蕉句碑 芭蕉句碑
高札場跡、:宿の京口にあたる。

言成地蔵:元は西の枡形辺りにあったがあまりにも落馬が多いのである武士が怒って斬ってしまった。地蔵は近くの新福寺に祀られたが寺も廃寺となり今はその境内の地蔵堂に安置されているという。

中央本線をくぐり牧野村に入る。
牧野の一里塚(日本橋より60里目)と馬頭観音(14:55)

南西方向へと30分ほど進むと左手に秋葉神社の祠と石仏群が見えてくる。(本山宿の東口)
 まっすぐに道はのびる。 まっすぐに道はのびる。
右手に「本山そばの里」の解説と看板。それによると本山は「そば切り」の発祥地。それまでは「そばがき」として食されていた。
発祥地には須原宿近くのの定勝寺ほか諸説あるようだがここもその一つだろう。

数少ないバスに乗る予定なので、この日は蕎麦を味わうゆとりがない。
~本山宿~

宿場の面影の残る旅篭、川口屋,池田屋、若松屋の三棟は喰い違いの斜交屋敷形式になっている。いずれも出桁つくりの風格ある建物だ。
 本陣跡 本陣跡 脇本陣跡 脇本陣跡
松本藩領、本山宿では尾張藩領に接しているため口留番所もおかれ、厳重な取り締まりが行われていたという。
高札場跡(15:50)
本山宿西口から、街道の行く先を望む。
東からの中山道はこの先で、木曽路へと入っていく。

15時58分発の地域バスで塩尻へ引き返す。
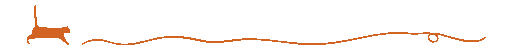
浮世絵より
洗場宿

宿の西を流れる奈良井川の夕景
本山宿

  塩尻へ 塩尻へ
|
|
|
![]()