早朝に出発しても佐久平に着いたのは13時32分。遅くとも14時には歩きはじめたいので先に切り上げた塩名田までタクシーを使う。先ずは中津橋で千曲川を渡る。心配していた天気も崩れることなく青空が広がっている。

橋の先は御馬寄(みまき)村。官牧望月牧の貢馬を寄せ集めたところを地名とする塩名田宿の加宿で、千曲川の渡しをつとめた。今は立派な橋も明治初年頃は9隻の船をつないだ舟橋がかけられていたという。(たもとの掲示板より)

御馬寄村の坂を登っていく。やがてちいさな板の表示があり右の小路を行く。野に白い腹がけを付けられた大日如来像が見えてくる。御馬寄の一里塚周辺には田園地帯が広がり、すでに稲刈りの済んだ田の向こうに今日もまた雄大な浅間山がすそ野を広げている。

道沿いの石仏。

①大日如来像と芭蕉句碑「涼しさやすぐに野松の枝のなり」
②井戸や湧水の守護神「御井大神」と二基の道祖神
③頭部にぼ梵字の刻まれた観世音菩薩碑
④井戸の守護神、生井大神と馬頭観音
やがて道の先に緑の森が見えてくる。あの辺りが目指す八幡神社だろうか。千曲川と鹿曲川と八幡神社の北の布施川に囲まれた広大な台地を御牧ヶ原といい、平安時代には「望月の牧」という官営牧場で朝廷に馬を献納していたという。

=
八幡宿=
集落に入った頃、右手バス停あたりが八幡宿の東口の様だ。

八幡神社:
貞観8年(866)御牧の管理をしていた滋野貞秀の創建と言われている。
江戸期造営で、数百本の欅材を使ったという随神門が堂々とそびえていた。門をくぐると、
本殿、拝殿の彫刻の見事さに驚いた。

高良社:扉の紋章など、見たところ再建かと思える旧本殿の高良社(1491)は国の重要文化財とされ、渡来人を祀っているという。

八幡宿本陣:皇女和の宮が泊ったというが、今は門のみが昔日を物語る。

八幡宿では千曲川の川止めに備えて4軒もの脇本陣、旅篭は3軒あったというが、今はこの本陣門のみの様だ。

八幡入り口のバス停先を斜め右の旧道に入る。間もなく馬頭観音

更に、国道と合するあたりが八幡宿の西口に当たる。

国道を500mほど行くと百沢東交差点。横断した後、右の旧道へ入り百沢集落の中を進む。
右の高みに祝言道祖神が祀られている。祝言道祖神とは安曇地方で発生した道祖神だが、このように宮庭衣装を見に付けた像は珍しいらしい。

布施温泉入口交差点で国道142を渡り県道150に入る。更に、元禄道標のあるところで草道に入る。旧中山道をたどるのはなかなか厄介


道なのか藪なのかといった小路を進むとやがて上り坂が見え国道へといった標識

国道を横断し、望月宿⇒の表示通りに金山坂を登る。

これでいいのかと不安になった頃に瓜生坂の一里塚(日本橋より45里目)

中山道瓜生坂の碑

斜め右の下り坂にはいり、やがて、長坂の向こうに望月宿が見える。

坂道の両側に次々と石仏。(道祖神や馬頭観音)

下りきると鹿曲川に突き当たり、長坂橋で川を渡る。遠くに見えるのは八ヶ岳だろうか?

この先は枡形になっていて、望月宿へと入っていく。
=望月宿=
望月の名は官牧、望月牧に由来する。望月城の姫に恋をした月毛の馬の民話「望月の駒」が語り継がれているという。もとは鹿曲川の右岸にあったが、洪水で流され左岸の現在地に移ったという。白壁土蔵、出桁造り、格子の屋根実が残っている。
駒の里というわけでわら馬が民俗資料館で販売されていると聞いたがあいにくしまっていた。
井出野屋旅館・・・大正5年築の木造3階建て

御宿山城屋・・・旅篭、山城屋喜左衛門で江戸時代末期の創業

大森本陣跡と斜向かいの鷹野脇本陣跡(藤棚のあるところ)

大和屋跡:真山家は旅篭と問屋を兼ねていた。望月宿最古の建物。

夕方でかなり光が陰ってきた。望月宿を振り返る。

大伴神社・・・望月氏の庇護をうけ、毎年8月15日に火祭りがおこなわれるという。


バス時刻を気にしながら少しでも先に進みたく、これといった見どころもない道を進む。
御桐谷西交差点の先まで行ったが、いよいよ佐久平行バス時刻が迫り、少し引き返したところから乗車。この日の宿のある佐久平へ向かった。
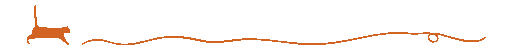
![]()