岩村田~小田井~追分

9月18日午後
追分から30分間ほどは右に姿を現した浅間山を道連れに歩くことになる。
標高は佐久平に向かって下がっていくので快適な歩きだ。逆に京からの旅人にとっては登りとなるためこのあたりに来て追分宿の灯りを見て笑みをこぼしたというので「笑坂」といった名も残っている。
12:00
千ヶ滝湯川用水温水路
慶安2年(1650)柏木小右衛門が開いた農業用水路で、戦後、千ヶ滝湯川用水温水路へと改修された。浅間山の雪解け水や湧水を水源とするので稲作には水温が低く、この施設で水温の上昇を図っているとのこと。
この水路を眺めながらのお弁当タイムとした。朝から歩きっぱなしの足を暫し休め、また快適な歩きが始まる。お天気もよく、浅間山の雲もどんどん流れ、長閑さがうれしい。

御代田観音像の脇に中北道標がある。目指す小田井宿までは3.4キロとある。まだまだ遠い

先ずは1Kmほど先の御代田一里塚へ田園風景も楽しみながら歩こう。
右に広がる浅間山への風景、土手のコスモスも美しい。


大久保橋で久保沢川を渡りしばらく行くと大山神社がある。

13:00
民家が並ぶ通りの右にうっかり見落とすような標識がある。
表示にしたがって登っていくと、街道から離れた畑の中に御代田一里塚(両塚)を見つける。
西塚の上には枝垂れ桜の大木。 
街道にもどり、地下道でしなの鉄道をくぐる.御代田駅の近くだ。
地下道を出たら右折し栄町交差点から旧道に入り荒町を通っていく。中山道を示す道路にひかれた緑の線がうれしい。脇に入ると、雄大な浅間山の姿。

13:30 中北道標(小田井宿 入口)
 おはる地蔵
おはる地蔵
傍らに「女傑、安川はる」と書かれた解説があり、
明治36年小田井にうまれ、高価な肥料が買えない農民のためにゴミと人糞から燻炭肥料を作る「安川式肥料燻炭炉」を発明した。指から入った菌によって体を侵されながらも写経にも励み、・・・・生涯地域のために貢献し、89才で永眠する。彼女の住居跡にこの地蔵が立てられたといった内容だった。

東枡形あたりには、東屋が立てられ、フクロウやクマの木彫りが置かれていた。
小田井宿は飯盛がなく婦女子の宿泊が多かったところから姫の宿ともよばれたという。
天保14年の大概帳によると宿内家数107、うち、本陣1、脇本陣1、問屋2、旅篭5軒で人口は316で男女の数はほぼ同じ。宿長945m。
 安川本陣跡 安川本陣跡
宝暦6年の改築後、和の宮降嫁の際にも改築されたという。和の宮はここで昼食をとり,その際、本陣は小さな人形を拝領。それにちなんで宿では毎年8月16日には拝領の人形を籠に載せ練り歩く小田井宿祭りがおこなわれているという。
上の問屋跡、(安川家) 宿を振り返って眺める。用水のせせらぎが聞こえる静かな宿だ。
宿を振り返って眺める。用水のせせらぎが聞こえる静かな宿だ。

脇本陣跡

長屋門を構える下の問屋 (尾台家)

旧旅篭の前には木製標柱

13:50
宿を後にして20分ほど歩いただろうか、中北道標のある小田井南信号で県道9号に合流する。
千曲バスのバス通りでもあり、各停留所を確認しながら歩くのも目安になっていい。
右手に松の緑の美しい一角がある。「皎月原」というらしい。
皎月原
この地には古くから皎月の輪に関する伝説があるらしく、解説板によると
「用明天皇元年(586)皎月という官女がおとがめをうけて、佐久郡の平尾へ流されてきた。いつも白馬を愛していた官女は、ある時小田井の原へ馬をひきだして乗りまわしていたが天の竜馬だった白馬は空へかけ上り、東西南北をかけまわった後、平尾山の頂上に立ちとどまった。そこで官女は「われは唯人ではない。白山大権現だ」といって光を放って岩の中へ入ってしまった。その後、官女を白山大権現というようになった。その後も皎月は時々小田井の原へきて、馬の輪乗りをした。そのあとには草が生えなかったので、そこを皎月の輪とよぶようになった」と。

車の多い通りを岩村田へと歩く。左の草むらに白い看板が見える。
思いがけないことに、そこが鵜縄沢端の一里塚だとわかる。中山道開設当初に設置された一里塚で東塚のみ現存している。

なおも車道を行く。道路の左側にリンゴ畑がつづくようになる。直売所なども設けられているようだ。手の届きそうなところにたくさん実っている。

上越自動車道の上を岩村田橋で越える。14:40
やがて、左手奥の草むらに石仏石塔が見える。千手観世音、馬頭観音などが並んでいる。

住吉神社
岩村田宿の江戸口にあたる。境内には樹齢400年という欅の大木がある。鳥居側から見ると
雷でも落ちたのか、火災にあったのか焼け焦げて空洞になっている。それでも見上げると見事にたくさんの葉をつけている。
龍雲寺
武田信玄が1560年に中興開基し、北信濃やに西上州への進出拠点とした。
伊奈駒場で亡くなった信玄の遺骨を禅師が持ち帰り納めたという。
屋根に武田菱が見られる立派な山門。
中山道は岩村田本町の商店街へと入っていく。
岩村田は内藤氏15000石の城下町で本陣も脇本陣もなく旅籠の数も少なかったが、経済の中心として栄えていたという。佐久甲州街道、下仁田道,善光寺道が交差し,米穀の集散地として商人が多かったという。名物は鯉料理であったとは内陸らしい。
予想より早く着いたが、もう一宿先へは5キロある。足もかなりくたびれている。宿をとってある
小諸へ引き返すべく、商店街の中ほど、西念寺念仏通りへと右折し、岩村田駅方面へと急いだ。意外と遠い。・・・
16:02発の小海線には下校時間の高校生が大勢乗っていた。
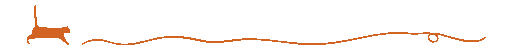
|
|
![]()