追分~沓掛

9月18日(午前)
2日目午前中は沓掛から追分。午後は岩村田駅までの予定で、おおよそ15.5キロ
8:34 中軽井沢駅(沓掛)

沓掛宿は安永2年の大火で壊滅的被害を受けるまでは、昨夕急いで通り抜けた旧道脇の
宮の前の一里塚(見落とした)から現在の駅裏を行く道筋にあったようだが、大火後は今の18号線沿いへと移転。小宿ではあったが草津温泉を控え湯治客でにぎわったという。天保14年の大慨帳によると,,家数166軒、うち本陣1、脇本陣3、旅篭17、人口502、宿の長さは668mであった。
宿は昭和26年にも大火に見舞われ、現在は碑がある程度で全く宿の面影を残していない。
国道18号、軽井沢方向へ目をやると早朝の離山にはうっすら霧がかかっている。

沓掛宿で見かけた宿の名残。

①八十八銀行の駐車場奥で見つけた脇本陣跡
②問屋も兼ねた本陣跡は門柱にはめ込まれた「本陣土屋」で確認できる。
③草津道への道標を兼ねた石仏。側面に「右くさつへ」と刻まれている。草津へは10里の道のり。
沓掛の西口もはっきりせぬまま中山道は国道と離れ左の旧道へとはいる。男女双体道祖神を右にみて、追分に向かっての堂坂を緩やかに登っていく。積まれた石垣の上のシュウメイギクが美しい。

道の両脇、浅間石でできた石垣が美しい。古宿辺りだ。

野の中に変わった文字の石柱が立っている。
近くへ寄って目を凝らすと梵字が刻まれている、もちろん意味は不明。
 ①梵字碑 ①梵字碑
②道祖神と、馬をつなぐ石柱
③廿三夜供養塔
④秋葉神社社殿脇の「阿天梨大神」碑。雨乞いの神らしい。
今日は降らせないでと祈る・・・
旧古宿村を登っていく。
路傍右手にに次々と馬頭観音が現れる。馬をつなぐ石柱も多い。
旧古宿村は当時、中馬、中牛の宿でにぎわった立場。
信州の農民が駄賃稼ぎに荷を運搬。「岡舟」と言われ、中継することなく直送したために荷崩れなく
安価だったので人気があったという。
 ①②③共に馬頭観音 ①②③共に馬頭観音
9:40
左手に方向を示すような自然石に馬頭観音と刻まれている。左折する道を指し示すようだ。その向かいに、この道の解説板がある。この道は女街道といわれ、「入り鉄砲に出女」の取り締まりが厳しい碓氷関所を避けた女人が利用した裏街道とのこと。

ここで左折せず、まっすぐ先へ、間の宿であったという借宿村を通る。
「おちこち」と読む神社があり、氏子さんだろうか、掃き清める姿が目に入る。境内はかなり広く苔むしてはいるが公園のようにもなっている。氏子さんとしばし話すと、社殿は享保年間の建立で御神体は浅間山だという。神社名の「遠近」は在原業平の[信濃なる浅間の巌に立つ煙 遠近人の見やはとがめん」にちなむのだとか。社殿前には業平が腰かけたと伝わる岩もあった。
追分までもう少しの登りだから頑張ってくださいと声掛けくださる。
地元の方と話すのも旅の楽しみだ。

左手に立派な建物
1670年に建てられ、後再建、改修もされて今に至っている土屋作右衛門家でその屋号を「ぬのや」といい。米穀問屋、酒屋、質屋、中馬業など幅広く営んでいた。左手にある蔵の前には「旧借宿村高札」が掲げられていた。

台上の大きな馬頭観音碑:この地で生活を支えてくれる馬がいかに大切にされたかが馬頭観音の多さからうかがえる。

再び道は国道18号と合し、その右手に「草津道分去れ道標」が立っている。

700mほど進んだところに追分一里塚(両塚) 10:25

道はY字形に国道と分かれ、右の静かな道へ入る。いよいよ追分宿だ。
天保14年の大概帳によると、宿家数103、うち本陣1、脇本陣2、旅篭35、
人口が712のうち、女性の数が大きく上回っているのは、北国街道分去れを控えての賑わいで、飯盛が大勢いたことを表している。
先ずは、右手山側にある郷土館にはいる。
茶屋を復元したコーナー、ひな人形、什器、鎧などが展示され
伝統民謡「追分節」を聞くコーナーもある。パカパカという馬の蹄音も入ってなかなか情緒ある民謡だ。飯盛女たちが三味線の伴奏を工夫して馬子唄を洗練させ、各地の追分節の源泉になったのだという。

郷土館隣りには浅間山の鳴動の鎮静祈願をしたという浅間神社があり、その境内に江戸時代に建てられた「ふきとばす石も浅間の野分けかな」という芭蕉の句碑があった。

街道へ戻ると左手に立派な門が見え、その先は整然とした緑の並木。
奥には、堀辰夫の文学館があった。並木入口の門は本陣裏門が移築されたもののようだ。

右手少しくぼんだ所に建つのは脇本陣油屋
油屋は元禄元年の創業で元の建物は向かいにあったが昭和12年の火災で焼失し移転したという
堀辰夫が「風立ちぬ」をかいたのはこの脇本陣の「つげの間」だという。

土屋本陣跡:土屋市左衛門が代々勤めたというが、いまは跡を示す表示のみ。

その隣に寛永年間の古文書に基づいて復元されたという高札場

公民館前にあった追分宿碑
再び国道と合するあたりが追分宿の京口。
ふりかえると
交差点左手前は枡形で、「枡形茶屋つがるや」がある。
建物二階の漆喰壁に浮き出た「枡形」と「つがるや」の文字が印象的。

国道を200mほど進むと、Yに道が分かれその分岐点が、
北国街道分去れ(追分)
寛永元年建立の常夜燈には「これより左、伊勢」と刻まれ、もうひとつの道標は「さらしなは右、みよしのは左」とあり、中山道は左へと進む。11:30

8時30分に始まった午前中に続き、午後は岩村田まで、倍近くの距離がある。
気合を入れて歩こう。
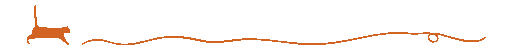
英泉の浮世絵
沓掛:湯川の流れる、多分一里塚近くだろうか

追分;追分原辺りの浅間山

 
|
|
|
![]()