贄川駅13時30分着

贄川宿は木曽十一宿の北境の宿、つまり、京方からだと木曽路最後の宿ということになる。

駅前の国道19号を南西方向へ少し歩き左折、関所橋で中央本線を越えると左手坂下に
関所が復元され、太い柱や石置き屋根が往時をしのばせる。
尾張藩領と松本藩領との領界に当たるため、北の要害として置かれた贄川関所では「入り鉄砲に出女」「木曽五木の搬出」を厳しく取り締まっていた。

天保14年当時は宿内家数124軒。うち、本陣1、脇本陣1、旅篭25、人口545人であったというが、昭和5年の大火でほとんどの建物が焼失
現在、本陣跡といったような標識もなかったが、木曽家の子孫千村家が勤め、問屋、庄屋も兼ねていた。
本陣だったのかなとも思える立派な門構の家。

麻衣廼神社への道:天慶年間(938~47)創建の神社で「麻衣廼」は木曽の枕詞

秋葉、津島神社前の水場。

脇本陣跡の標識もなく宿内はひっそりとしている。
往時の様子をうかがい知れるのは寛永7年(1854)建築という深沢家住宅。
屋号を加納屋といい、行商を中心に財をなした商家は木材をふんだんに使った整然とした構えで江戸時代末期の木曽地方の町屋建築の到達点を示す建物と言われている。

やがて道は右折。枡形状に進み跨線橋で中央本線を越え国道と合流
しばらく行くと、右手山側にトチの大木が見える。
推定樹齢千年、樹高33m、根元の周囲17.6m天然記念物。

しばらく行くと「安くてうまい食事のデパート」があり、大勢の客の姿があった。
更に進むと
桜宮跡:馬頭観音、地蔵尊などの石仏が並び桜の古木がそれらを覆っている。後日、桜宮ってなんだろうと思って調べたがよくわからなかった
。

たくさんの幟が閃いている。ちょうどこの日「木曽漆器祭」が催されているようだ。
この先に木曽路民芸館があり、所狭しと漆器類が並べられ、たくさんの買い物客でにぎわっている。お買い得という木製スプーンを6本購入。もっと見たかったが先を急ぐ歩き旅だ。
民芸館の前を過ぎ、国道に沿った、金網の仮設歩道を進み、更に突き当たりの仮設階段を登ると旧道に出る。さっきの喧騒がうその様な草道で涼しい風が吹き抜ける。傍で中仙道碑も確認。


いかにも旧道らしい鳥居に出会う。「素盞鳴尊」ときざまれている。津島神社の主祭神だ。
このあたりには津島神社が多い。
国道とに挟まれた狭いところに押込の一里塚跡がある。日本橋より63里目だそうだ。
辺りを押込沢というらしい。
桃岡橋を渡る。下の清流れは奈良井川


この先、中央本線ガードをくぐり、国道、県道、さらに国道、県道と合流を繰り返し、炎天下の1時間をひたすら歩く。
物見坂を緩やかに登る。

塩尻市贄川支所の敷地に入ると芭蕉の句碑
「送られつをくりつ果ては木曽の秋」
諏訪神社:大宝8年に創建された。朱塗りの本殿が特徴的
階段を下り県道に合流。
右手に長野銀行が見える辺りからが旧平沢村(間の宿平沢)
特徴ある建物群
万延二年(1861)の大火の後、防火対策として奥行きの深い町割りとし、隣との間に余地を残
し、奥には塗蔵とよばれる白壁土蔵がつづいている。
街道がゆるやかに曲がっている地区では建物が雁行。街路に斜向かいに建ち、側面が連続して見える。


古くから漆器の生産が盛んで街道沿いには隙間なく漆器店が並び、この日は特に漆器祭でにぎわいをみせている。せっかくだから店をのぞいたり、お土産も買って漆器祭りを楽しんだ。
左に木曽平沢駅をみて、うるしの里公園を見下ろすあたりでしばし休憩。

JR中央線のガードをくぐると奈良井川の土手道。川沿いの快適な道を行く。歩道橋で対岸へ渡った所に橋戸の一里塚を確認。
元の道へ引きかえし左手の楢川小学校内に入ってみる。立派な木造校舎は木曽ならではだ。

この学校では給食の食器も木曽漆器が使われているとのこと。
川沿い道はやがて国道と合流、奈良井川橋を渡る。川に沿って大きく左折、しばらく川沿いを行く。(平沢方向を振り返る)
奈良井踏切を渡ると左手に奈良井駅が見えてきた。町歩きを楽しんだので17時前に着くのは無理だろうから奈良井宿でお茶でも飲んで時間つぶしをと思っていたが、思ったより近かったことに気がつき、これなら走れば16時56分に間に合いそうだ。明日に備えてできるだけ早くホテルに着くに越したことはない。ゆとりをもって歩いてきたが最後は走って飛び乗るということになった。
16時56分塩尻行き
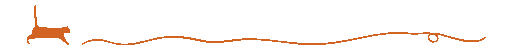
|
![]()