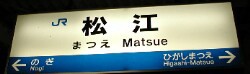11月5日(水)
START 10:10〜FINISH 16:40
![]()
11月5日(水)
![]()
![]()
START 10:10〜FINISH 16:40
| 松江駅10:10ー(バス&歩15分)ー10:25普門院・観月庵10:35ー(歩10分)ー10:45明々庵11:15−(歩)ー 11:20武家屋敷ー小泉八雲旧宅・八雲記念館12:20ー八雲庵(食事)12:50−(歩10分)ー 13:00松山城13:30−(歩20分)ー13:50月照寺14:10−(歩15分)ー松江温泉駅ー電車(一畑電鉄)− 15:00ルイス・C・ティファニー庭園美術館16:20ー(バス)ー16:40松江駅 |
 |
|
| 普門院は松江城を築いた堀尾吉晴により創建された天台宗の古刹。2度の移築を経て1689年この地におちついた。 茶室観月庵は1801年に建てられ、松平氏七代藩主治郷(不昧)もたびたび茶会を催したといわれている。 門前の「ふもんいんばし」は小泉八雲の怪談「小豆磨き橋の怪談」に描かれている。 また、日本野鳥の会を創設した中西悟堂が大正11年ごろ住持した寺でもある |
 北堀にかかる宇賀橋と塩見縄手沿い北堀の紅葉 |
 |
 |
茶人として有名な七代藩主松平不昧公の好みにより、 松江市殿町に建てられたもので 2畳台本席と4畳半の席を持つ茶室。 一時東京に移されたこともある。 戦後荒廃していたものをs41年、不昧公150年祭を記念しこの地(赤山)に移された。 |
 長屋門と塀 |
 約265年前の古い姿のまま保存されている。母屋は約70坪 表側の式台玄関から座敷にいたる公の部分と、裏側の私生活部分は造りも材質も区別し 武家の公私の別の厳しさが伝わってくる。 また、家族の居間よりも主人の部屋が広いこと、茶室、仏間といった小部屋も備えていることなど 外から全部屋を見ることができ興味深かった。 甲冑や家具類、化粧道具、台所用品などが展示され当時の生活をかいま見ることができた。 |
 井戸 水まわりは東側にあり直ぐ傍に井戸 |
 台所(外) 汲んだ水を甕に入れると・・・ |
 台所(内) ・・・中で使えるように工夫されている。 なるほど! |
 1890年から約1年3ヶ月間、島根県尋常中学校で英語教師を務めたが その間、小泉セツと結婚、この家は5ヶ月間住んだ。 八雲は東京で亡くなるまでの14年間日本で過ごし、 その間松江、熊本、神戸、東京と移り住み10軒もの家で暮らしたが 当時のまま現存するのは庭のある武家屋敷に住みたいと願って借りたこの旧居のみである。 |
|
 |
 |
| 「知られぬ日本の面影」の舞台となった庭園と八雲の書斎 | |
 |
 |
| 亀田橋 | 椿谷散策コース |
 |
 |
| 天守閣 |
6階の望桜からは松江市街が一望できる |
| 天守閣・・・築城時のまま現存する。望楼式を加えた複合天守で外観5層、内部6階 壁は黒く塗った雨覆板(下見板)で覆われている。実戦本意の武骨な体裁で壮重雄大な感じがする。 天守閣内部・・・地階には深さ24メートルの井戸もあり、篭城にそなえた生活物資の貯蔵庫になっている。 2階には敵が近づくと石を落とせるように石落としがある 階段は軽くて引き上げやすく、防火防腐効果のある桐がつかわれていて、他に類がない。 柱は肥え松の柱の外側に板を添えて寄せ合わせ金輪で閉めて太くしている。 |
|
 |
 |
| うっそうとした杉木立の中 それぞれの廊所にはj特色ある廊門が設けられている。 |
大亀 八雲の随筆にも登場する「月照寺の大亀」 市中で暴れたため動けないよう石を載せられたと いわれている。 |
 |
 |
 |
| 美術館入り口 | イングリッシュガーデンの噴水と ステンドグラスが美しいチャペル |